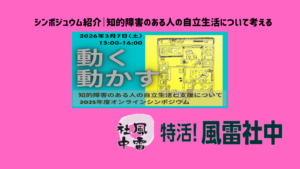文責 中村和利
1. 「外出できない」は小さな問題ではない
移動支援(ガイドヘルプ)の大切さを語る時に、まず「外出」の大切さを考えて欲しい。
障害がないと言われる多くの人たちは、さまざまな制約や制限はある中でも、基本的に「自由」に外出をすることができる。
外出が公的に制限されているのは、1類〜3類の危険な伝染病に感染した場合や犯罪を犯し収監された場合だ。COVID-19感染防止の記憶は、まだ新しいだろう、COVID-19の時でさえ「自粛」だった。あれだけ同調圧力での社会的な抑制が働く中でも政府による法的な強制は限定的で、「要請」や「自粛」という枠組みが中心だった。それだけ、人の外出の自由は重要な権利=人権であるのだ。
「外出の自由」は、医療、教育、仕事、友人関係、社会参加など人間らしい暮らしの基礎となる権利であるのだ。
2. 知的障害のある人とガイドヘルプの経緯
しかし、実質的に外出が制限されている人たちがいる。
単独での移動に困難がある重度障害のある人たちだ。
そして、その状況は近年まで「自己責任」もしくは「家族で解決すべき問題」とされ、公的な支援などない状況が長く続いていた。特に知的障害のある人たちは身体的なケアの必要が認められにくく、また社会参加の意義も低くみられていた状況があった。
知的障害のある人たちの外出の権利は家族や一部の良心的なボランティアに依存する形で支えられてきた。
先行して始まっていた視覚障害のある人たちのガイドヘルプをモデルに、1987年には大阪府枚方市で、知的障害のある人へのガイドヘルパー派遣が市単独事業として始まったとされている。
その後、1993年には大阪市、1998年には横浜市で制度化され、やがて国の制度としての「移動介護」へと位置づけられていった。こうした市町村レベルの取り組みは、やがて国の制度にも影響していく。2003年に始まった支援費制度の下で初めて全国的な公的制度として認められた。そのことにより滞留していた外出の希望が一気に表面化し、各地で予算が急激に膨らんだ。
補正予算の連続は制度運営に大きな負担となり、その一因として、外出支援は「法定給付」ではなく、自治体が裁量で実施する地域生活支援事業の中に再整理された。これは、外出支援を制度として残すためであると同時に、財政上の膨張を抑制するための措置でもあったと考えられる。その是非については賛否諸説あるところだろう。ただし、地域生活支援事業に整理されたことで外出支援そのものを公的に位置づける全国的な枠組みは整えられた。
支援費制度でのニーズ爆発からも、いかに、必要とされ「求められている」社会保障なのかがわかる。
同じ時期、国際社会では障害者権利条約が採択され、「地域で暮らし、社会に参加する」という方向性が明確に示された。障害者基本法改正、障害者自立支援法(現在の総合支援法)、差別解消法、虐待防止法など日本の障害のある人を巡る法制度の変化は、この国際的潮流とも重なりながら、少しずつ形を整えていった。
3. 法制度の変化と「外出の自由」の再定義
ここで話を最初に戻そう。
「外出の自由」は重要な人権であり、危機的な緊急事態でなければ一般市民が制限されることはない。
そして、障害者権利条約や改正障害者基本法、差別解消法などの国内法でも理念として「障害を理由」に障害のない人と人権の差別があってはならないことが定められている。この理念をベースに障害による困難は環境の整備や調整によって最大限解消される方向へと法制度はリデザインを求められ、一見ゆっくりと、歴史的にみたら急速に改正をされてきた。
知的障害のある人の外出の自由を支える移動支援も「困っている人への善意の施し」ではなく、法制度の中で、権利を保障する仕組みとして位置づけられ、未だ不十分ではあるが運用されてきている。
移動支援は人権を保障するための合理的配慮であり社会基盤であり、数ある障害福祉サービスの中でも、基本的人権の根幹の一角を担う重要な制度なのだ。
外出できない、ということは——
通院・買い物・人に会うこと・余暇のすべてが難しくなる、ということだ。
つまり、生活のほぼすべてに影響が出る。
4. 「外出が奪われる」とき、何が失われるのか
ここからは、僕自身の経験や現場で見てきたことも交えながら、少し肩の力を抜いた言葉で考えてみたい。
では、その移動の自由が損なわれた時(保障されなかった時)に、人は何を「失う」のだろうか?
ここまでの論でも、その人自身が手に入れるべき経験や様々な権利を行使する機会を逸することも重要だが、ここではもう一つ側面を確認していきたい。
人間は自身の所属する内集団と自分とは違う外集団に人を区分けしていく。
同じ学校である、同じ街に住んでいる、友人グループ、会社、そして家族といった集団を作り、その内の人と外の人を分けていく。このこと自体は人間の自然な認知だと言われている。これが、外される人を“見えなくする”働きを持つ。良し悪しの話ではない。
この論の前半で移動の自由と人権について記したが、これを読んだ多くの人は「そんなことは知っている」と思ったのではないだろうか?社会の中の多くの人たちは「知っている」のだ。
しかし、知的障害のある人たちの権利を公的に保障していくことが難しい原因の一つは、多くの人が知識としては知っていても、「自分たちの問題」として捉えていないからではないかと僕は考えている。
僕らの暮らす街には自らの力で動く事が困難な要介護高齢者が暮らす特別養護老人ホームがある。
ホームで暮らす高齢者の状態や、充分とは言えないスタッフ数でケアが日々提供されていることを僕らは知識として知っている。
もし大規模災害があった時に顔も名前も知らない高齢者を助けに行く近隣の人はどれだけいるだろうか?
僕自身もその時に自分がどう行動するか疑問だ。しかし、そこに顔も名前も知っている知り合いの高齢者が住んでいたら、どうする?間違いなく可能な限り手助けに行きたいと思うのではないだろうか?
重度知的障害のある人たちの多くは知的障害のある子どものための学校や学級に行き、オトナになると知的障害のある人のための施設で活動をする。単独での外出に困難がある場合は買い物や余暇など街にでる機会も少ない。
これは多くの障害のない人たちと知的障害のある人たちが、場や経験を共有し、知り合う機会を共に逸しているのだ。知的障害のある人たちは、社会や街のメインストリームを構成する人たちにとって顔も名前も知らない、場や経験の共有のない外集団の人たちとなり、想像の外に置かれているのではないだろうか。
このことにより重度知的障害のある人の多くが社会のメンバーシップを保留されてしまっていると僕は考えている。
5. 「他人ごと」になる構造と社会合意
知的障害のある人への社会保障が進みにくい大きな要因は、この分離された状況による社会合意の形成だと僕は考える。
人権は大切だと重々承知な多くの人たちが、それでも知的障害のある人たちの社会保障について「他人ごと」になっている。これは無理解でも悪意でもない、分離と分断が生み出す「状況」だ。
僕は縁があり若い時から知的障害のある人たちと時間を共にすることが多くあり、みんなの暮らしの状況が整備されていかないことに不満を感じていた。そのことを福祉とは関係のない友人や知人と話した時に「わかるけど仕方がないんじゃん」といなされたことが何度となくある(そんな時代でもあった)。
その時僕は心のなかで『(知的障害のある人の)顔や名前を知ってから、それでもそう言えるなら言ってみろ』と思っていた。
もちろん、顔や名前を知るだけで、なにもかもが変わる訳ではない。ただ、そこからしか始まらないのだ。
知的障害のある人たちのメンバーシップの保留状態が分離と分断による構造的問題であるなら、その構造を変えていくしかない。そこで重要になるのがインクルーシブ教育であり、障害のある人の一般雇用だろう。
人は人生の多くの時間を学校と仕事に費やしているし、家族以外の他人と知り合いや友人になる機会の多くはそこなのだから。しかし、インクルーシブ教育や障害のある人の一般雇用が進まない根本原因の一つは、知的障害のある人たちが「メンバーシップを保留されたまま」社会の外側に置かれていることにある。
つまり、社会参加がないから理解が進まず、理解が進まないから社会参加も進まない——というループが続いている。
6. 小さな一歩としての「外出」
そこで小さな取り組みかもしれないが「外出」が重要になる。
制度や効率化社会の壁に阻まれている教育や仕事の場は、ゆっくりとしか進まない。そして、その進展には社会合意の変容が必要になる。社会合意の変容を促す一つの鍵が、知的障害のある人たちの「外出」なのだと僕は考えている。それも、家族というグループでの外出ではなく、ガイドヘルパーというアシスタントを引き連れた「一個人」として街に参加していき、その存在が社会のメインストリームに認知されていくことで、メンバーシップ保留の膠着状態を溶かしていけるのではないだろうか。
前例はある。街のバリアフリーが進んだのは、重度身体障害のある人たちが車椅子でバリアフルな街に出かけていくことが「間違いなく」推進力になった。目の前の人の存在が社会に与える影響の大きさを証明している。もちろん、それだけで変わってきた訳ではないし、これからもそれだけで変わる訳でもない。しかし、障害のある当事者が街に出て、社会に参加してメンバーシップを機能させていくことを抜きには進まないと僕は考えている。
7. ガイドヘルプが生み出す「出会いのし直し」
ある知的障害のある青年のガイドヘルプで、一緒にコンビニに買い物に行った時、レジが混んでいたので、いつもだったら青年は自分でお財布からお金を出すなど支払いの受け渡しをゆっくりだけどやっていたのに、僕が焦ってしまい。僕がやるねとお財布から支払おうとしたら、レジをしていた店長さんが「ああ、ゆっくりで大丈夫ですよ。いつも通りに本人にやってもらって」と笑顔で声をかけてくれた。
ある知的障害のある青年と、青年の家の近くのカフェに一緒に通っていたら、ある日、店の人が「彼、一人でも外出して買い物してるのね。こないだスーパーで見かけたよ」と話しかけてくれた。そして、どんなことが困るのかな?そんな時に見かけたら、なんて声をかければいいかな?と色々と聞いてくれた。
休日にガイドヘルプで初めて知的障害のある人と接点をもった会社員さんは、会社には言ってなかったのに、上司から「最近、人のことを待てるようになったね。うまく出来ない人へも良い接しかたをしているよ」と評価されたことを嬉しそうに教えてくれた。
ガイドヘルプは街の人たちと知的障害のある人たちの緩やかな「出会いのし直し」だと僕は思っている。そして、その出会いは様々なシチュエーションと小さいけど確かな何かを生み出してくれる。
9. ガイドヘルパー養成研修のためのクラウドファンディングへ
ここまで書いてきたことを、ごくシンプルに言い換えると、こうなります。
「制度はあるのに、外出できない人がいる」
その静かな生活制限をほどいていく鍵のひとつが、ガイドヘルプなのです。
しかし そのガイドヘルプを支える担い手が、決定的に足りていない。
ガイドヘルプは、制度さえあれば自動的に回る仕組みではありません。
一人ひとりの知的障害のある人のそばに立ち、街に一緒に出ていくガイドヘルパーがいなければ、どれだけ制度が整っていても、現実の外出は生まれません。
現在、風雷社中を含め、多くの現場ではこうした矛盾を抱えています。
- 移動支援や居宅介護の報酬は、目の前の利用希望に応えるための人件費と調整業務でほぼ使い切られてしまう
- 本来必要な「ガイドヘルパー養成研修」や、担い手を増やすためのアウトリーチにまで、継続的なコストを回しにくい
- その結果、「制度はあるのに、ヘルパーが足りないから外出を断らざるを得ない」という状況が生まれてしまう
制度の枠組みだけを眺めれば、移動支援は「すでにあるサービス」です。
けれど、現場から見ると、担い手を育て、支え続けるための基盤はまだ十分とは言えません。
だから今回、風雷社中は「ガイドヘルパー養成研修」に特化したクラウドファンディングに取り組むことにしました。
- 行政の制度改正を待つだけでなく、
- いま必要とされている外出のニーズに応えるために、
- 市民と一緒に、担い手を増やすためのコストを支えるしくみをつくりたい
ガイドヘルプは、一部の「特別な人たち」のための話ではありません。
いつか自分や家族が、支援を必要とする側になるかもしれない社会で、
「外出の自由」というごく当たり前の人権を守るための社会インフラだと僕は考えています。
今回のクラウドファンディングは、そのインフラを維持・拡張していくための、とても小さな、しかし具体的な一歩です。
この一歩を、一緒に踏み出してくれる人を募る——それが、風雷社中のクラウドファンディングの目的です。
【クラファン開始】ガイドヘルパー養成研修を続けるために、ご支援をお願いします
NPO法人風雷社中では、ガイドヘルパー(知的障害者移動支援)を育成する養成研修を継続して実施してきました。しかし資金不足により、毎年の継続開催は、とても厳しい状況です。今年度の研修費用の補填と、来年度開催に向けた準備のた […]
10. おまけ|施設ケアとガイドヘルプの「構造」の違い
僕は「ガイドヘルプは重要な取り組み」であることをことあるごとに語っている。
それは知的障害のある本人の人権保障として、社会や街のコミュニティとの「出会い直し」の機会としての重要さとして。しかし同時に、ただ顔や名前を知っているだけでは状況は良くならないのである。
ガイドヘルプは朝や夕方に30分から長くて3時間くらいにニーズが集中しやすい。マンツーマンの対応なので、短時間のニーズが同時刻にあれば、その数だけのガイドヘルパーが必要になる。一見、非効率な話なのだが、マンツーマン=一対一であることにはとても意味がある。
ここで分かりやすくするために施設と対比させてみよう。
施設は基本的に効率的なケアのためにデザインされてるので、一人のスタッフが複数の利用者の対応をすることになる。そこでは個々の特性や気持ちよりも集団としての効率が優先されることになる。また「施設」というスタッフサイドが管理維持する箱に利用者を迎え入れることで、主客の力関係の逆転が起きやすくなる(逆転させた方がスタッフたちはスムーズに業務を遂行しやすくなる、と思ってしまう)。
施設での知的障害のある人とスタッフの関係は、利用者主体との合言葉とは裏腹に、集団的な効率性優先であり、対等から程遠いものになりやすい構造だ。そこでの「出会い直し」は関係性の修復に機能しにくい。施設を全て否定するつもりはなく、現状の社会合意の中で知的障害のある人の暮らしを成立させるために必要な機能を担っていることも思う。しかし、その構造に大きな課題があることは押さえておきたい。
ガイドヘルプは一人ひとりの知的障害のある人の傍らにたち、やや少し後ろから、本人の視線を追って街を見る。そして、本人の困っていることに一緒に取り組んでいく、それも本人のためのペースや個々に併せたコミュニケーションをとり、本人の希望を一緒に実現していく立場にたつ。この立ち位置に立つことは、街でたまたま出会うこととは、また違う濃密さがあり、互いのアイデンティに触れ合う関係の入口だと思っている。そして、ガイドヘルパーを担う人材の多くは、ガイドヘルパーをやるまでは知的障害のある人と出会う機会を逸していた暮らしを続けてきた「普通の人たち」である。
ガイドヘルプは、ただの外出のお手伝いなのだ。だからこそ、静かにしっかりとした、知的障害のある人と、障害のない人が「出会い直す」小さな、でも確かな構造を作り上げているのです。